
このページでは、
「仕事を辞めたいけど保育園はどうなるの?」
「転職を考えているけど退園の心配が…」
という不安をお持ちのママたちに向けて、やさしくわかりやすく解説していきます。
退職・転職しても保育園を継続できる?基本ルールを解説
そもそも保育園の「利用要件」とは?
保育園は、ただ子どもを預かってくれる場所というだけでなく、保護者が安心して働いたり、必要なサポートを受けたりするために設けられている施設です。
そのため、利用には「保育の必要性」が求められます。
具体的には、
「保護者がフルタイムまたはパートタイムで働いている」
「病気や出産、介護などで日中の保育が困難」
「求職活動中」
「就学中」
などの事情が含まれます。
これらの状況があることで、子どもを保育園に預ける正当な理由とされるのです。
保育園継続の可否を判断するのは誰?
保育園を継続利用できるかどうかは、保育園自体が判断するのではなく、保護者が住んでいる地域の市区町村(自治体)が審査し、決定します。
保育の必要性があるかどうか、また提出された書類に不備がないかなどをチェックし、判断を下します。
そのため、園の先生に聞くだけでなく、自治体の窓口にしっかり確認することが大切です。
退職=即退園ではない理由と猶予期間
退職をしたからといって、すぐに子どもが保育園を退園させられるわけではありません。
多くの自治体では、「求職中」として一定期間、保育園の利用を継続できる制度を設けています。
この期間は一般的に最大で90日間とされており、その間に新しい就職先を見つけることで、引き続き保育園を利用することが可能です。
ただし、猶予期間中も求職活動をしている証明(記録や届出書の提出など)が必要で、放置すると退園につながることも。
しっかりとスケジュールを立て、自治体への報告を忘れずに行いましょう。
保育園の種類によって対応が違う?
認可保育園と認可外保育園の違い
認可保育園は、国や自治体の基準を満たした施設であり、運営費の一部を公費でまかなっているため、保育料も所得に応じた設定となっています。
そのため、比較的安価で安心して預けられる反面、申し込み時には細かい条件や審査が必要で、定員オーバーのために入園が難しい場合もあります。
また、就労証明書などの提出書類が多く、手続きの負担も少なくありません。
一方、認可外保育園(無認可保育園)は、国の基準に基づかずに設置された施設ですが、その分柔軟な対応が可能です。
たとえば、夜間保育や延長保育など、家庭の状況に応じて柔軟に利用できる施設も多くあります。
保護者のニーズに合えば非常に便利ですが、費用は認可園よりも高めに設定されていることが多く、施設によってサービスの質にも差があるため、事前の見学や口コミの確認が重要です。
自治体によって対応が異なることも
同じ日本でも、住んでいる自治体によって制度や対応が大きく異なることがあります。
たとえば、就労証明書のフォーマットや求められる提出期限、求職中に利用できる期間の長さなどが異なるケースがあります。
また、一部の自治体では認可外保育園を利用していても保育料の補助が出るところもあるため、最新情報は必ずお住まいの自治体の窓口か公式ホームページで確認しましょう。
電話での問い合わせや、子育て支援窓口での相談もおすすめです。
在宅ワーク・フリーランスでも保育園利用はできる?
フリーランス・自営業が求められる証明書類とは
会社員と違い、フリーランスや自営業の方は勤務先が明確ではないため、自分自身で就労している証拠を提示する必要があります。
主に「開業届(税務署への届出書類)」や「業務委託契約書」、「請求書・納品書」などが該当します。
これらの書類を提出することで、きちんと収入を得ている仕事であることを証明できます。
また、事業用の名刺やウェブサイトのスクリーンショット、SNSでの活動履歴なども参考資料として認められる場合があります。
自治体によっては、収入の実態をより具体的に確認するために、確定申告書(青色申告・白色申告)などの提出を求めることも。
複数の書類を組み合わせて提出することで、信頼性が高まります。
就労実態の確認方法
在宅でのお仕事の場合は特に、「本当に働いているのか」が見えにくいため、実態を丁寧に証明する必要があります。
たとえば、日々の作業時間を記録した勤務表やスケジュール表、仕事内容のレポート、クライアントとのやりとりの記録などを求められることがあります。
自宅でパソコンを使って行う仕事でも、業務の内容や納期などを具体的に示すことで、保育の必要性を証明することができます。
提出書類に迷った場合は、必ず自治体の保育課に相談するのが安心です。
書類を用意するだけでなく、活動実態を「見える化」して丁寧に伝える姿勢が大切です。
保育園に預けながら退職・転職する際の具体的な流れ
ステップ①:退職が決まったらまずやること
退職が決まったら、まず最初に行うべきなのは、お住まいの自治体への相談です。
保育園の継続利用には自治体への手続きが必要なので、早めに連絡することがとても大切です。
相談の際には、退職する日付や、次にどのような働き方を考えているか(転職予定があるか、しばらく求職活動をするかなど)を具体的に伝えましょう。
また、必要な書類や今後のスケジュール、求職活動中のルールなどをあらかじめ確認しておくことで、後々慌てることがありません。
可能であれば、電話だけでなく一度窓口で話をすることで、個別の事情も踏まえたアドバイスを受けることができます。
ステップ②:求職活動中に必要な対応
退職後すぐに新しい仕事が決まらない場合は、求職中として保育園を利用するための手続きが必要になります。
多くの自治体では「求職活動中届出書」の提出が求められます。
この届出書には、どのような仕事を探しているのか、どのくらいの頻度で活動しているのかなどを記入します。
また、実際に求人へ応募した履歴や面接の予定などを記録・報告する必要がある場合もあります。
こうした証明ができないと、保育の必要性がないと判断され、退園となる可能性があるため注意が必要です。
スケジュール帳や活動記録をきちんと残しておくと、万が一提出を求められたときにも安心です。
ステップ③:転職が決まった後に提出する書類
無事に転職先が決まったら、次に行うのは「就労証明書」の提出です。
これは新しい勤務先に発行してもらう書類で、勤務開始日や労働時間、雇用形態などが記載されます。
できるだけ早めに人事担当者などにお願いして、記載漏れのないように確認しましょう。
また、雇用契約書のコピーや勤務スケジュールの提出を求められることもありますので、用意しておくとスムーズです。
提出が遅れると、保育の継続に影響する場合があるので、早めの対応を心がけましょう。
ステップ④:自治体の判断と通知の流れ
すべての必要書類を提出すると、自治体での審査が行われます。
内容に問題がなければ、数日〜数週間で「保育継続承認」の通知が届きます。
通知が来るまでは不安な気持ちになるかもしれませんが、事前に丁寧な準備をしていれば心配はいりません。
通知が届いたら、保育園側にも報告をしておきましょう。
また、自治体によっては不備があれば連絡をもらえるケースもあるので、連絡先を明確にしておくと安心です。
提出書類と注意点まとめ【求職中・転職済みの場合】
退職後「求職中」になる人の必要書類
・求職活動届出書
・転職活動の記録(応募先・面接日など)
・ハローワークや転職エージェントなどの相談履歴
・求職活動スケジュールや求人検索履歴(スクリーンショットでも可)
これらの書類を提出することで、「現在しっかりと求職活動をしている」という姿勢を示すことができます。
特に自治体によっては、活動の「頻度」や「具体性」を重視されることもあるため、実際に応募した履歴や日付、応募先企業の名称などを記録しておくと安心です。
また、何社応募しても不採用になった場合でも、活動実績を残していれば「保育の必要性がある」と見なしてもらいやすくなります。
退職後すぐ転職する人の必要書類
・新しい勤務先の就労証明書
・雇用契約書のコピー
・勤務開始日が明記されたスケジュール表(提出が求められる場合あり)
すでに次の就職先が決まっている場合は、書類の提出も比較的スムーズです。
ただし、就労証明書には勤務時間や就労形態(フルタイム・パートなど)を正確に記載してもらうことが必要です。
記入漏れや不明点があると、再提出を求められる可能性もあるため、提出前に内容をよく確認しておきましょう。
雇用契約書や内定通知書など、補足資料があるとさらに安心です。
自治体によっては「給与見込み証明」や「勤務日数の内訳」を求められるケースもあるため、念のため事前に確認しておくとよいでしょう。
就労証明書の記載ミスに注意!
就労証明書は、保育園の継続利用において非常に重要な書類です。
内容に不備があると、再提出を求められるだけでなく、審査が遅れる原因にもなります。
特に注意したいのは「労働時間」や「雇用期間」の記載です。
例えば、フルタイムで働いているはずなのに労働時間が短く記載されていると、「保育の必要性が低い」と判断されてしまう可能性もあります。
また、雇用開始日や勤務形態(正社員・パートなど)も漏れなく記載されているかを確認しましょう。
記載ミスを防ぐためには、会社の担当者に丁寧に説明し、必要な情報を正確に伝えることが大切です。
可能であれば、書類作成前に自治体のサンプルを見せると、記入漏れが減らせます。
提出猶予期間を厳守しよう
退職後に保育園の利用を継続するには、自治体が定める「提出期限」内に必要書類を提出しなければなりません。
多くの自治体では、「退職後14日以内」「求職開始から30日以内」といったルールがあります。
この期限を過ぎてしまうと、「保育の必要性が証明されなかった」として退園になる可能性が出てきます。
提出書類は複数に及ぶこともあるため、退職が決まった段階でカレンダーにスケジュールを登録しておきましょう。
また、自治体のホームページで提出書類一覧をダウンロードしたり、チェックリストを作成しておくと、漏れなく手続きを進められます。
家事や育児で忙しい日々の中でも、リマインダーアプリなどを活用するのもおすすめです。
猶予期間を過ぎたらどうなる?
提出期限を過ぎてしまった場合、必ずしも即退園になるわけではありません。
やむを得ない理由(急病、家族の介護、自然災害など)がある場合は、まず自治体に事情を説明し、相談してみましょう。
誠意をもって報告すれば、状況によっては猶予期間の延長や再審査といった柔軟な対応をしてもらえることもあります。
ただし、「なんとなく忙しかった」「忘れていた」といった理由では厳しい判断をされることも。
普段から提出スケジュールや必要書類のリストを手元に置いておき、少しでも遅れそうな場合は早めに自治体へ連絡を入れることが重要です。
トラブル回避の第一歩は「早めの行動」と「丁寧な説明」です。
保育園に預けたまま仕事を辞めたいときの選択肢
退職前に自治体へ相談して確認を
退職を考え始めた段階で、できるだけ早めにお住まいの自治体へ相談に行きましょう。
自治体の窓口では、退職予定日や今後の就労予定について伝えることで、今後必要になる書類のリストや提出期限、保育継続に関するルールなどを詳しく教えてもらえます。
また、各家庭の事情や自治体ごとのルールの違いもあるため、早い段階で確認しておくことで安心して行動できます。
特に「求職中」としての猶予期間の有無や期間、必要書類の内容、証明の方法などは自治体ごとに異なることがあるため、「自分の場合はどうなるか」を聞いておくのが大切です。
電話だけでは伝わりにくいこともあるので、できれば窓口での相談をおすすめします。
ママ向け転職エージェントの活用
育児と両立しながらの転職活動は、想像以上に大変です。
そんなときは、ママに特化した転職エージェントを活用してみましょう。
時短勤務や在宅勤務OKの求人、子育て理解のある企業など、ママ向けの働き方に理解のある職場を紹介してくれるケースも多く、一人で求人を探すよりも効率的です。
履歴書や職務経歴書の添削、面接対策などもサポートしてくれるので、ブランクがある方でも安心して転職活動を進めることができます。
エージェントに相談することで、今まで気づかなかった選択肢に出会えることもあるため、まずは気軽に登録・相談してみるのがおすすめです。
無職期間を短くする転職スケジュールの立て方
退職後の無職期間が長くなってしまうと、保育園の継続利用が難しくなったり、収入の不安が続いたりと、心身ともに負担が大きくなってしまいます。
無職期間をなるべく短くするためには、退職のタイミングと転職先の内定時期をしっかり逆算し、あらかじめスケジュールを立てておくことが大切です。
具体的には、退職日の2〜3か月前から転職活動を始めておくと安心です。
求職期間中にも自治体への報告や証明書類の提出が必要になることがあるため、準備には余裕を持ちましょう。
また、できる限り在職中に次の仕事が決まるように進めることで、保育園の手続きもスムーズに行えます。
面接日や内定が決まった時点で、保育園や自治体への連絡もしやすくなりますし、安心して退職・転職ができるようになります。
求人応募〜面接〜内定後の動き方
気になる求人を見つけたら、できるだけ早めに応募することが大切です。
求人はタイミングによってはすぐに締め切られることもあるため、こまめな情報チェックとスピード感が成功のカギになります。
応募後は、書類選考や面接の日程が決まり次第、早めに保育園や自治体にその旨を伝えましょう。
特に面接日はお迎えの時間調整や一時保育の利用が必要になることもあるため、早めの相談がポイントです。
また、内定が出たらすぐに「就労証明書」の取得を新しい勤務先に依頼し、必要書類とあわせて自治体へ提出する準備を進めましょう。
このように、転職活動の一つひとつのステップで自治体や保育園と連携を取りながら動くことで、無職期間を短くしつつ、保育園の継続利用をスムーズに進めることができます。
転職・退職が保育園の選考や加点に与える影響は?
加点が消える可能性のあるケース
保育園の選考では、家庭の状況によって加点が付与される仕組みがあります。
たとえば、ひとり親世帯であることや、両親ともにフルタイムで働いている場合などは、優先順位が高くなるため加点が加えられます。
これは、保育を必要とする度合いが高いと見なされるためです。
しかし、こうした加点は、就労状況の変化によって簡単に失われてしまうことがあります。
特に注意したいのが「退職」や「時短勤務への変更」といった就労状況の変化です。
これにより、翌年度の入園申請時に加点がなくなり、同じ保育園に継続して通うことが難しくなる場合もあります。
待機児童の多い地域では、わずかな加点差が合否に影響することもあるため、加点が失われることの影響は軽視できません。
転職や働き方を見直す際には、次年度の保育園申請のタイミングと重ならないように調整するのが理想です。
次年度入園申請への影響と対応策
退職や勤務時間の変更など、保護者の就労状況が変わった場合には、その情報を速やかに自治体へ届け出ておく必要があります。
来年度の入園・継続申請の際に、現在の状況と実際の働き方に違いがあると、「虚偽申告」と判断される可能性もあるためです。
たとえ不利になるとしても、正しい情報を提出することが大前提となります。
また、次年度の申請を有利に進めるためにできることもあります。
たとえば、転職が決まっている場合は新しい勤務先の就労証明書を事前に準備しておく、フルタイム勤務に戻す予定があるならばその計画を記載して提出するなど、具体的な再就労の意思を示すことが信頼につながります。
自治体によっては、再就労予定を記載する「意向書」などを添えることで、一定の配慮をしてもらえる場合もありますので、迷ったときは担当窓口に確認してみましょう。
加点の有無や申請内容は保育園の選考に大きな影響を及ぼします。
だからこそ、日々の就労状況と申請書類の整合性を保ち、トラブルを防ぐことが重要なのです。
入園決定後に転職・退職したらどうなる?
就労状況の変更を放置するとどうなるか
就労状況に変更があったにもかかわらず、保育園や自治体へ報告を怠ってしまうと、重大な影響が出る可能性があります。
たとえば、保育の必要性がないとみなされて「入園取り消し」になることも。
これは一度決定されてしまうと覆すのが非常に難しく、再入園も困難になる場合があります。
また、報告義務を怠ることで自治体との信頼関係も損なわれてしまい、今後の保育利用に影響するケースも少なくありません。
実際に「短期間だから報告しなくてもいいだろう」と思っていたら、後日自治体から連絡が来て事情説明を求められた、という声もよく聞かれます。
ですので、たとえ一時的な就労状況の変化であっても、早めに自治体へ相談し、指示に従って正しい手続きを行いましょう。
相談することで、状況に応じた柔軟な対応をしてもらえることもあります。
後で慌てないためにも、変更があった際は必ず届出を行うことが大切です。
入園取り消しの可能性も?注意点まとめ
保育の必要性が自治体からないと判断されてしまった場合、保育園の継続利用は非常に難しくなってしまいます。
これは、保育園が本来「保育が必要な家庭」を優先して支援するための制度であるためです。
そのため、たとえ一時的に働いていない期間があっても、求職活動の証明や再就労の予定があることをしっかりと伝えることが重要です。
また、自治体との信頼関係は、保育園の継続や次年度以降の申し込みにおいても大きく影響してきます。
必要書類の提出を怠ったり、虚偽の申告をしたりすると、保育の必要性が認められないだけでなく、今後の保育サービス利用に不利になることもあります。
たとえば、以前に提出遅延や報告不足があった家庭には、再申請時により厳しく審査されるケースもあるのです。
そうした事態を避けるためにも、少しでも状況に変化があったら、速やかに自治体に相談し、正確な情報を届け出ることが大切です。
保育園を安心して利用し続けるためにも、「正確な手続き」と「丁寧なコミュニケーション」を心がけましょう。
保育園を一度退園すると再入園は難しい?
保育園の再入園の現実と倍率の高さ
一度保育園を退園してしまうと、再び入園するには最初の入園時と同様に申請と審査を受けなければなりません。
特に人気のある保育園では応募者が殺到して倍率が非常に高くなることがあり、希望するタイミングで再入園するのは簡単ではありません。
たとえ以前通っていた保育園であっても、優先的に受け入れてもらえるとは限らないのが現実です。
保育園の空き状況は時期や地域によって大きく変わるため、事前に自治体の最新情報をこまめにチェックしておくことが大切です。
また、兄弟が同じ保育園に通っていたとしても、再入園においては別枠での審査となることもあるため注意が必要です。
再入園時に必要な申請とポイント
保育園に再入園する際には、初めての入園時と同じように各種の申請手続きを行う必要があります。
就労証明書、家庭状況調査票、その他自治体が指定する書類の提出が求められます。
中でも、就労証明書の内容は再入園の可否を左右する大きなポイントとなるため、勤務時間や雇用形態などを正確に記載し、不備がないように気をつけましょう。
また、再入園の際には申請時の「優先順位」や「加点制度」が審査に影響するため、現在の家庭状況がどのように評価されるかを理解しておくことが重要です。
たとえば、ひとり親世帯である、フルタイム勤務である、兄弟がすでに在園しているなどの条件が加点対象となることがあります。
これらの条件は自治体ごとに異なるため、詳細は必ず事前に確認し、不安がある場合は窓口で相談するのがおすすめです。
よくある質問Q&A
Q1:父親が転職する場合も手続きが必要?
はい、必要となる場合があります。
保育園の継続利用に関する手続きは、家庭全体の就労状況を確認する目的で行われることが多く、父親の転職もその対象に含まれるケースが多々あります。
特に、共働き家庭で両親の就労をもとに保育園の利用が認められている場合、父親の就労状況が変わることで保育の必要性に関する判断が変わる可能性があります。
そのため、転職が決まった時点で速やかに自治体へ相談し、必要書類の提出について確認することが重要です。
Q2:就労証明の記載はどこまで必要?嘘はバレる?
就労証明書には、勤務先名、勤務開始日、就労時間、雇用形態、仕事内容など、基本的な情報を正確かつ具体的に記載する必要があります。
たとえば、フルタイム勤務かパート勤務か、在宅勤務なのか出社型なのかといった点も重要な判断材料となります。
もし記載内容に虚偽があり、それが発覚した場合、保育園の退園や過去に遡った保育料の返還を求められることがあります。
また、自治体によっては就労実態を電話や書類で確認するケースもあるため、誤魔化しは通用しないと考えたほうがよいでしょう。
正確な情報を提出することで、安心して保育園を利用し続けることができます。
Q3:短期の離職でも保育園は継続できる?
短期間の離職であっても、基本的には猶予期間が設けられており、その期間内に次の仕事が決まれば保育園の利用を継続できます。
多くの自治体では、退職後90日間を上限とした求職期間が認められており、この期間中に求職活動を行っていることを証明できれば、引き続き保育園に子どもを預けることができます。
ただし、猶予期間中に何の連絡や活動報告もしなかった場合には、退園を求められる可能性もあるため注意が必要です。
あらかじめ自治体に短期離職の可能性や次の就職の見込みについて相談しておくことで、よりスムーズな対応が期待できます。
実際の体験談とよくある失敗例・成功例
書類の提出忘れで退園になりかけたケース
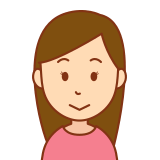
仕事や育児に追われる日々のなかで、うっかり保育園への提出書類の締切を忘れてしまい、ある日突然、園から『退園手続きに入ります』と通告されてしまったんです。
まさかの事態にパニック状態でした。
提出猶予期間の存在も知らず、慌てて自治体に相談して事情を説明し、何とか退園を免れました。
忙しい毎日でも、スケジュール帳やスマホのリマインダーで書類提出日を管理しておくことの重要性を痛感しました。
開業届で在宅ワークを証明できた成功例

ライターとして自宅で仕事をしていたものの、収入が不安定なため保育園の継続利用ができるか不安でした。
そこで、開業届を税務署に提出し、これまでの仕事の履歴や納品書、請求書をまとめて自治体に提出したところ、就労の実態がしっかり確認できたとして保育継続が認められました。
あらかじめ保育課に相談して必要な書類を確認していたことが、スムーズな審査につながったと思います。
フリーランスや自営業の方は、事前準備が何よりも大切です。
就労証明書の不備でトラブルになった事例
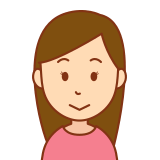
転職先からもらった就労証明書に記載ミスがあり、実際よりも短い労働時間で記載されてしまいました。
自治体から不備として連絡があり、再提出が必要になってしまったのです。
書類の内容確認を怠ったことが原因でした。
会社の人事担当者に確認し、正確な勤務時間や雇用形態を記載してもらい、無事再提出できましたが、タイミングによっては審査に時間がかかることもあるそうです。
就労証明書は保育の継続に直結する重要書類なので、記載内容はしっかり確認すべきです。
保育園継続利用の手続きを忘れないために
チェックリストで重要項目を確認
保育園の継続利用に必要な準備を、もれなく進めるためにチェックリストを活用しましょう。
以下の項目を参考に、退職・転職の状況に応じて確認してください。
-
✅ 退職日を把握し、スケジュールに登録する
-
✅ 自治体の保育課へ相談の連絡を入れる(窓口・電話)
-
✅ 「求職活動届出書」や「就労証明書」などの提出書類を確認
-
✅ 書類提出期限(猶予期間)をカレンダーやリマインダーで管理
-
✅ 求職活動の記録を残す(応募履歴・相談記録・面接日など)
-
✅ 新しい勤務先が決まったら、就労証明書を早めに依頼する
-
✅ 書類の記載内容(労働時間・勤務形態など)にミスがないか確認
-
✅ 自治体の公式ホームページで最新の情報・様式を確認
-
✅ 必要であれば、子育て支援センターや転職エージェントに相談
-
✅ 進捗を1週間ごとにチェックして、手続き漏れを防止
自治体の公式ページを事前にチェックする
お住まいの自治体の保育課や子育て支援課の公式ホームページには、保育園に関するさまざまな情報が掲載されています。
退職や転職に伴う手続き、求職中の保育利用のルール、就労証明書の提出方法、必要な書類のダウンロードリンクなどがまとまっているため、まずは必ず目を通しておきましょう。
特に注意したいのは、自治体によって取り扱いが微妙に異なる点です。
たとえば、求職期間の上限日数や必要な証明書の内容、様式の指定(フォーマットが決まっている場合)などが自治体ごとに違っていることがあります。
「他の人の体験談と同じだろう」と思い込まず、自分の住んでいる地域のルールを正確に把握しておくことが大切です。
また、公式ページには「よくある質問」や「申請の流れ」が図解付きで説明されていることも多く、手続き初心者にもわかりやすい構成になっています。
書類の提出先や問い合わせ先の連絡先、受付時間なども記載されているため、事前に確認しておくことでスムーズに行動できます。
スマホから簡単にアクセスできるため、ブックマークしておくのもおすすめです。
さらに、必要書類のPDFをダウンロードして印刷しておけば、いざというときに慌てず対応できるでしょう。
サポートを受けられる窓口・相談先まとめ
退職や転職に伴う保育園の手続きは、初めての方にとっては不安や疑問がつきものです。
そんなときに心強い味方になってくれるのが、自治体や専門機関の窓口です。
困ったときや迷ったときは、一人で悩まず積極的に相談することをおすすめします。
自治体の保育課・子育て支援課
まず最初に頼るべきは、お住まいの市区町村にある保育課や子育て支援課です。
保育園の継続利用に関する申請書類や手続きの詳細、提出期限、現在の状況に合わせたアドバイスなど、最も正確で具体的な情報を提供してくれます。
また、求職活動中の保育利用についても自治体によってルールが異なるため、自分のケースにあった案内を受けることが大切です。
事前に電話やオンラインで予約が必要な場合もあるため、自治体の公式サイトで窓口の対応時間や連絡先を確認しておくと安心です。
訪問の際には、保険証や身分証明書、現在の勤務先や退職予定に関する書類などを持参しておくとスムーズに進みます。
ハローワーク(公共職業安定所)
ハローワークは、保育園の継続利用に必要な「求職活動の証明」としても活用できる重要な機関です。
求人検索だけでなく、職業相談や履歴書の添削、職業訓練の紹介なども行っており、再就職に向けたサポートを幅広く受けられます。
また、面談を受けた記録や就職活動の履歴を残すことができるため、自治体への提出資料として活用することもできます。
お住まいの地域のハローワークを一度訪ねて、担当者に状況を説明しておくと安心です。
子育て支援センター・地域の保育コンシェルジュ
地域の子育て支援センターや、自治体が設置している保育コンシェルジュのような相談窓口も、気軽に利用できる頼れる存在です。
保育園に関する情報の提供や、家庭の状況に合わせた選択肢のアドバイスを受けることができ、退職や転職後の生活についても一緒に考えてくれます。
一人で抱え込まず、第三者に相談するだけでも気持ちが軽くなるものです。
ママ同士の情報交換の場としても活用できるので、ぜひ活用してみてください。
転職エージェント・ママ向け就職支援サービス
最近では、子育て中のママ向けに特化した転職エージェントや再就職サポートのサービスも増えています。
自宅からでもオンラインで相談できる場合が多く、自分の希望やライフスタイルに合った職場探しをサポートしてくれます。
働く時間や勤務地、福利厚生など、子育てとの両立を重視した条件で求人を紹介してくれるため、無理なく次の仕事に進むことができます。
履歴書や職務経歴書の添削、面接対策などのサポートも受けられるので、転職活動が初めてでも安心です。
ここまで読んでくださって、ありがとうございました。
少しでも不安が和らいで、「これなら私もできそう」と思っていただけたら嬉しいです。
何か迷ったら、まずは自治体や専門家に相談してみてくださいね。


